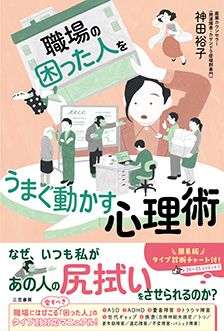https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=00401500
言うまでもなく、私は職場の困った人だ。
最近、それについて産業カウンセラーが書いた本が出て、ほとんど予想通り炎上している。
一方で、この本のマーケ対象はこの本に批判的な人たちではない。他人と合わせて働くことのできる人々の方が多数派であり、それがために経済活動が動くという事実は否定できない。だから、他人に合わせて働けない人は売上にならない困った人、というわけだ。
ただ、「困った人」なるカテゴリーを同僚に向ける人たちは、言動を理解するパターンに乏しい人が多い。困った人たちは、同じノリの同じ仲間としかつるんでこなかったみたいに思われるが、私はどっちもどっちのように思う。それでも、同じノリであれば業務コミュニケーションコストが非常に下がるので、効率的に感じるし(実際に効率的とは言ってない)、みんな困った人に困っているわけだ。
私は管理職なので、上記のように、ここで意図されていることそのものはとてもよくわかる。ただし、私は困った人であるにもかかわらず、なぜか管理職をやっている。どうしてそんなことができるかというと、私は人を困った人扱いする人間をそもそも信用していないからだ。そうした人間の欺瞞も「困った人」とされる人々の振る舞いも等価にパターン化された言動にしか見えない。
例えば、親密度とチーム業遂行能力が比例しているという考え方がある(正しいとは言っていない)。もちろん、困った人の筆頭である私は職場の飲み会には一切行かない。私の業務範囲で売上に繋がらないからだ。人を困った人扱いする人のうち、親しくないと働きづらい人は現実に存在するが、私にはどうしようもない。私は好き嫌いなく働くしかないし、同じチームにいる人間の得意不得意を判別して不得意を減じて得意を増やすようにしかできない。私は好きも嫌いもないので、あなたも人を好きとか嫌いとかで判断して働くのはやめてください、というのしかない。ちなみに、私が飲み会に行く時は、誰かが退社する時だ。その人が会社の人と仲良く過ごす最後の時にやってくる見送り人というわけだ。私はいつも別れの準備ができるようにしている。
最後に、少し真面目に考えてみると、これは管理職と管理職予備軍向けの自己啓発書なわけだ。産業カウンセラーが書いているからこういう語り口になるし、それで現実に救われている人もいる。ただ、これが総じて差別的かといえば、差別的だ。これを武器にして診断の下りている人を攻撃する愚か者が溢れかえるだろう。
そもそも、人を困った人呼ばわりするような人々の考えがちな、コミュニケーションをなんとかしたら問題が解決するというのは神話にすぎない。人間を大切するために人格や性格というものをあまりにも価値をおいてはいけない。道徳は人間を超えて存在するものなのであり、性格や人格、診断、そんな卑小な尺で判断してもどうしようもない。人間を大切にするために人を人として見ないこと。すべてを客観性とシステムに落とし込むこと。効率化を人間を否定するシステム化ではなく、多様な人間を同一システムで働くことができるような工夫だと理解すること。結局のところ、『アンチ・モラリア』をもう一度人は読み返すべきなのだろう。